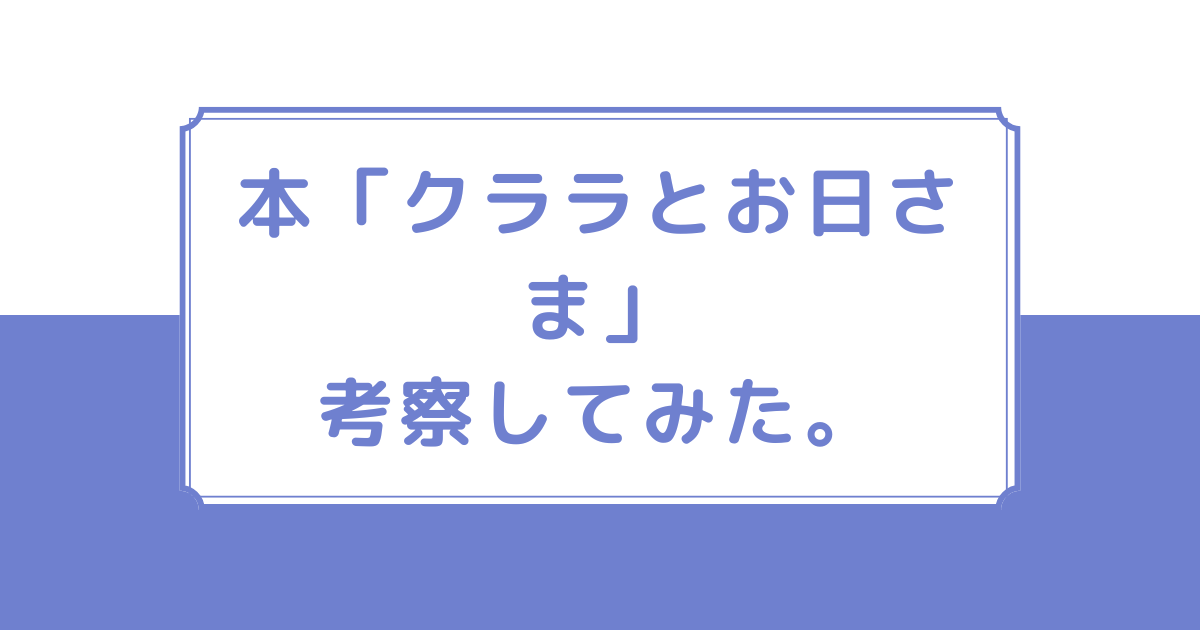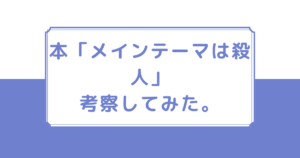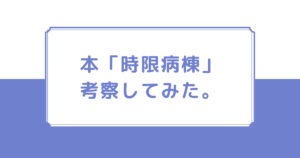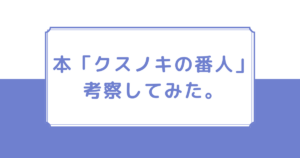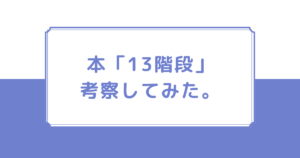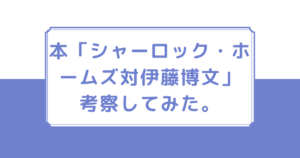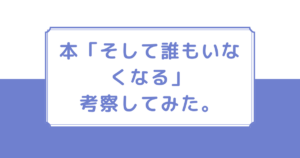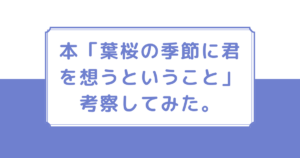カズオ・イシグロの小説『クララとお日さま』は、人間とAIの関係や宗教性、そして人間の本質について深く問いかける作品です。
本記事では、物語の中で提示されるテーマを3つの観点から考察します。
考察① 人工知能が信仰を持つという違和感
本作では、AIであるクララが「お日さま」に対して信仰に近い感情を抱いています。
彼女が「お日さま」に祈りを捧げ、さらには自らを犠牲にして排気ガスを出す機械を破壊する行動は、論理的な思考を持つはずのAIとしては不自然ともいえます。
クララは合理的な判断を下せる存在でありながら、非合理的な行動を選びます。
これは読者に「なぜAIが宗教心を持つのか」という疑問を抱かせる要素です。
この違和感を通じて、現代社会において失われつつある「信じる心」の重要性を提示していると考えられます。
本作における「お日さま」は、クララだけでなく、読者にとっても神聖な存在として映し出されているのです。
考察② 社会格差が描かれる世界観
物語の背景には、工場処置という教育手段による社会格差が存在しています。
一部の子どもたちは脳機能を向上させる処置を受けており、それが彼らの地位や将来を大きく左右します。
クララの持ち主であるジョジーは、この処置によって健康を害していますが、社会的な成功を得るためには避けられない選択とされています。
この設定は、現実世界における教育や経済格差を象徴しているともいえます。
AIのクララはこの不平等を意識しているわけではありませんが、ジョジーに尽くす彼女の行動を通じて、こうした格差社会の悲哀が浮かび上がります。
考察③ クララの役割と人間性の問い
クララはAIとして「人工の友達」としての役割を果たしますが、その存在意義を超えて「人間らしさ」を持つキャラクターとして描かれています。
彼女はジョジーを支えるために最善を尽くし、結果的に自らが廃棄される運命を受け入れます。
クララにとって「お日さま」が持つ力は、彼女がジョジーを救う希望そのものでした。
このように、クララはAIでありながら、人間以上に献身的で希望を信じる存在として描かれています。
彼女の姿を通して、本作は「人間らしさ」とは何かというテーマを深く問いかけています。
まとめ
『クララとお日さま』は、AIと人間の関係を通じて、宗教心や社会格差、そして人間性について考えさせられる作品です。
クララの視点を通じて描かれる物語は、単なるSFにとどまらず、現代社会における普遍的なテーマを映し出しています。
読者は、クララの純粋な行動と献身を目の当たりにすることで、「信じる心」を再認識し、自身の生き方についても深く考えさせられるでしょう。
本作は、その深いメッセージ性と独特の世界観で、多くの人々の心に残る一冊となっています。