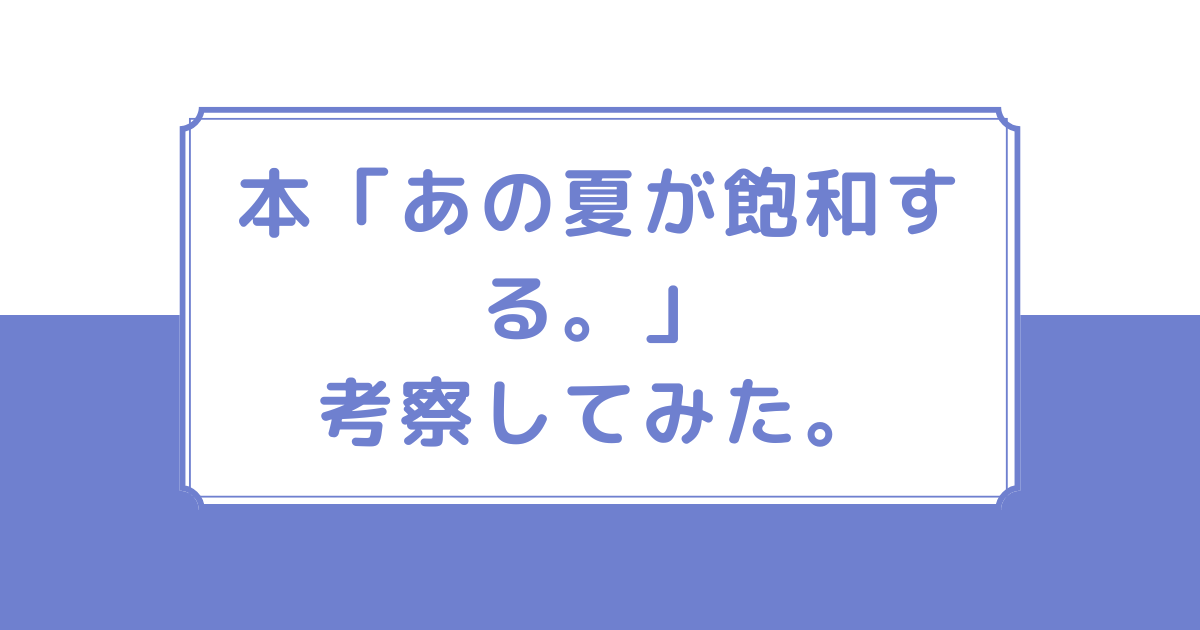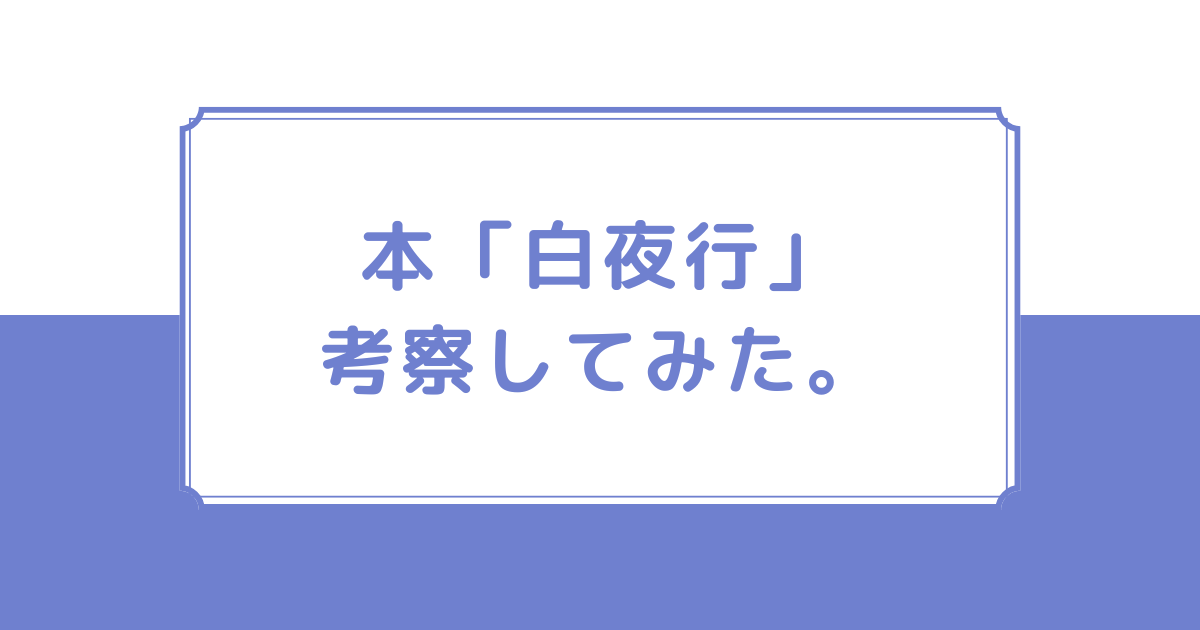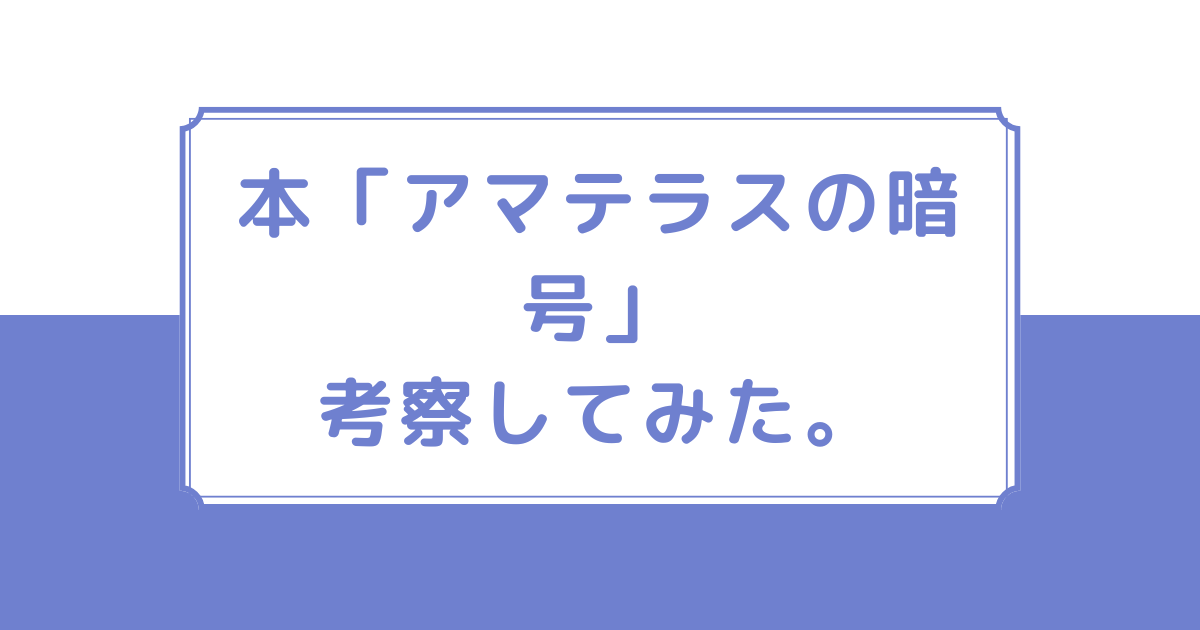神崎伊織の小説**「あの夏が飽和する。」**は、同名のボーカロイド楽曲を原作とした物語です。
ボカロ曲の世界観をさらに掘り下げ、小説ならではの視点で描かれた作品となっています。
物語の根底には「取り返しのつかない喪失」と「過去への執着」というテーマが流れており、読み進めるほどにその深みを感じさせます。
本記事では、小説「あの夏が飽和する。」に込められた意味やメッセージについて、3つの視点から考察していきます。
考察① 取り残された「僕」の視点
物語の中心にいるのは「僕」という少年です。
彼は、ある少女の不在を受け入れられず、夏の記憶の中に閉じ込められています。
彼の中では少女の死が確定しているわけではなく、「どこにもいなくなった」という曖昧な形で語られます。
これは、喪失を受け入れられない人間の心理を巧みに表現しているといえます。
また、作中で繰り返される「君だけがどこにもいない」という言葉は、彼の絶望と執着を象徴しています。
現実では時間が流れ続けるのに、彼の心はあの夏に縛られたままです。
この視点から考えると、物語は単なる悲劇ではなく、「残された者の苦しみ」を描いたものだと読み取ることができます。
少女の死よりも、「僕」がどうやって喪失と向き合うのかが焦点となっています。
考察② 「線路」と運命のメタファー
作中では「線路」が重要なモチーフとして登場します。
「線路の上を二人で歩く」という場面は、青春の象徴であると同時に、運命の暗示でもあります。
線路には決まった終着点があり、一度進み始めたら引き返すことは難しいです。
このことは、少女の死が避けられない運命だったかのような印象を与えます。
しかし、「駅で切り返すこともできたはずなのに、そのまま進んでしまった」という表現もあります。
これは、彼らの運命が完全に決まっていたわけではなく、選択の余地があったことを示唆しています。
この解釈に立つと、物語は「運命に抗えなかった物語」ではなく、「抗うことができたのに、それを選べなかった物語」へと変わります。
少女が選んだ道、そして「僕」が何もできなかったことの意味を、改めて考えさせられます。
考察③ 「飽和する」という表現の意味
タイトルにある「飽和する」という言葉には、単なる「満ちる」という意味以上のものが込められています。
作中で「頭の中が飽和している」と語られる場面がありますが、これは少年の心の状態を表しています。
思い出があふれかえり、もうそれ以上抱えきれない状態です。
現実と過去の境界が曖昧になり、どこにも行き場がなくなります。
その結果として、「僕」は前に進むことができず、過去の記憶に閉じ込められてしまいます。
また、2020年バージョンの楽曲MVでは、記憶が薄れていく様子が視覚的に表現されていました。
これは、「飽和」した後、次第に思い出が色褪せていく過程を暗示しているのかもしれません。
この視点から見ると、物語の「飽和する」という言葉には、「忘れたくないのに、やがて忘れてしまう悲しみ」が込められているとも解釈できます。
まとめ
「あの夏が飽和する。」は、単なる喪失の物語ではなく、**「喪失を受け入れられない者の視点」**を描いた作品です。
線路というモチーフを通じて運命の不可逆性を示しながらも、そこには選択の余地があったことを示唆しています。
そして、「飽和する」という表現を通じて、思い出に縛られ続ける苦しさと、やがて記憶が薄れていく切なさが描かれています。
物語の中で「僕」は、少女の不在を受け入れることができませんでした。
しかし、読者は彼の視点を通じて、「喪失とどう向き合うべきか」を考えさせられます。
本作を読んだあと、もう一度楽曲「あの夏が飽和する。」を聴いてみると、違った視点でその世界観を感じ取れるかもしれません。