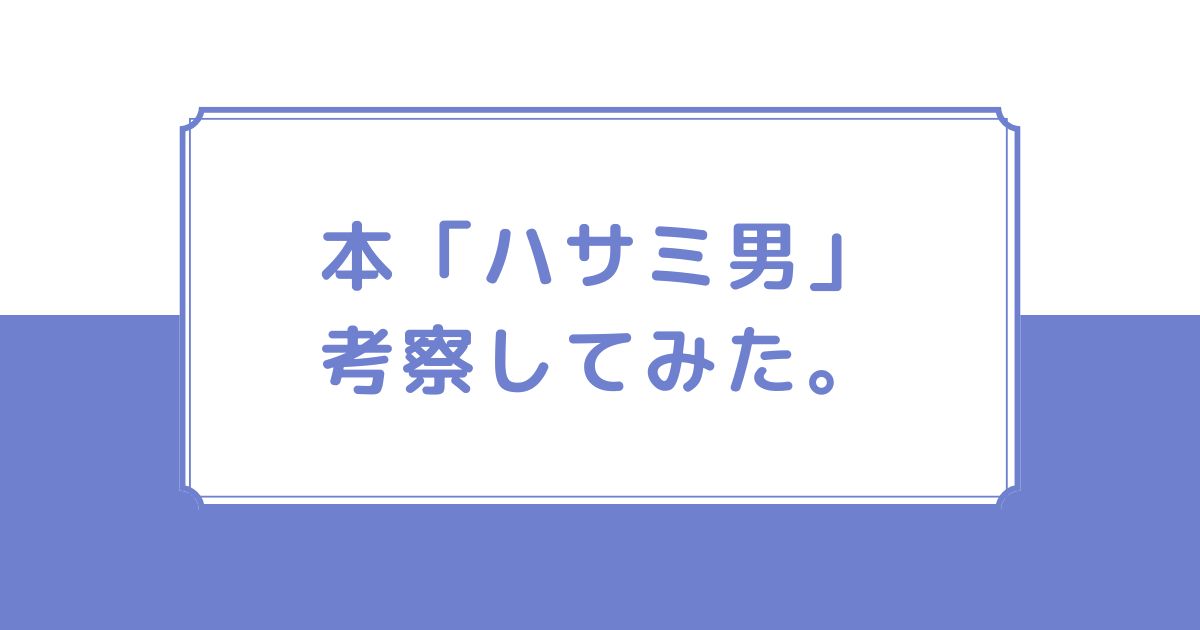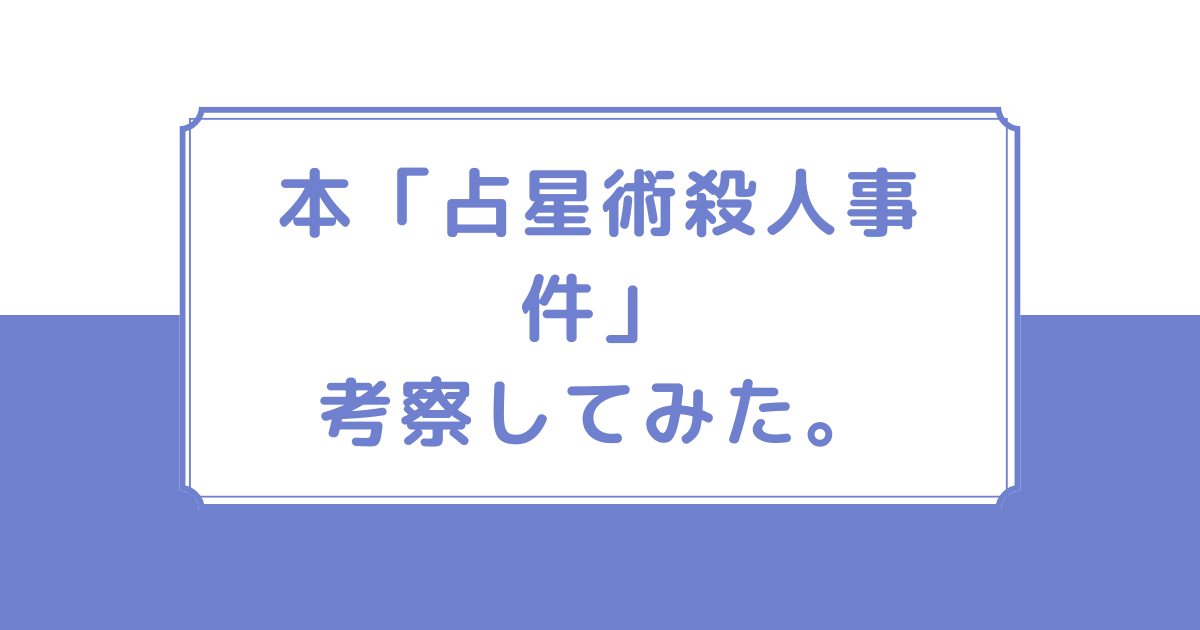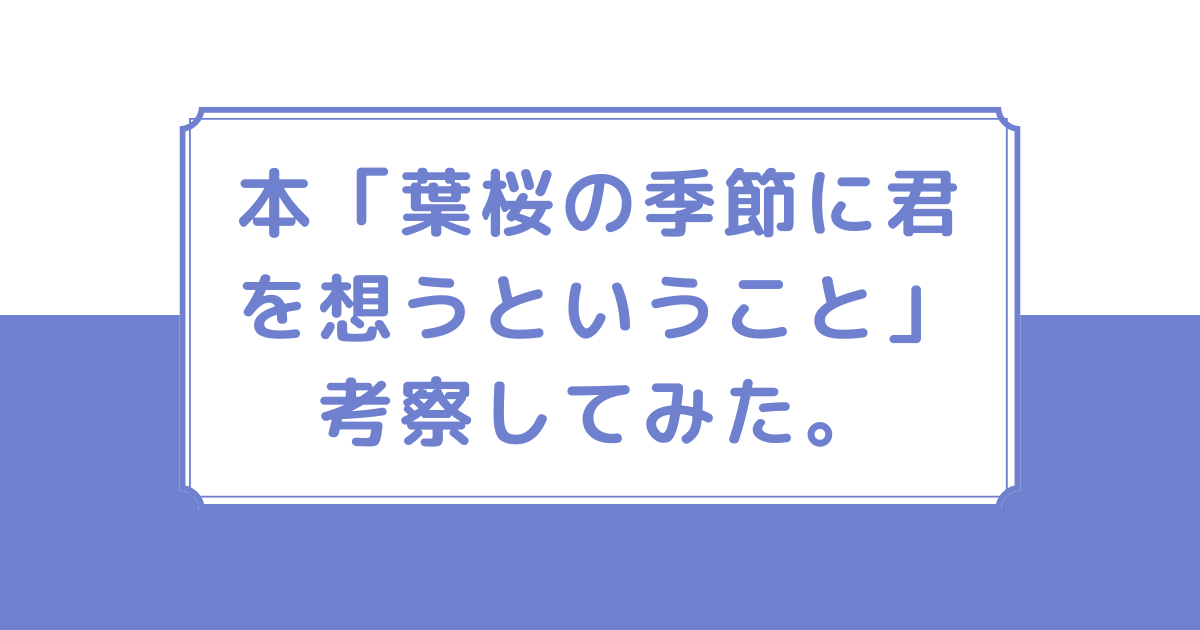殊能将之のデビュー作『ハサミ男』は、倒叙ミステリーと本格ミステリーを融合させた作品として、多くの読者を驚かせてきました。
物語は、連続猟奇殺人犯である「ハサミ男」の視点から描かれますが、彼が模倣犯による事件に巻き込まれたことをきっかけに、真相が明らかになっていきます。
本記事では、この作品の魅力を考察し、どのように読者を巧みに欺く構造が作られているのかを掘り下げていきます。
考察① 二重のどんでん返しが生む衝撃
『ハサミ男』は、どんでん返しの巧妙さが際立つ作品です。
特に、物語の終盤に用意された二重のどんでん返しは、読者の予想を大きく覆します。
物語は、ハサミ男の視点から進行し、彼自身が新たな被害者を選定している過程が描かれます。
しかし、彼の手口を模倣した殺人事件が発生したことで、彼は犯人ではない立場へと追いやられます。
この時点で、「ハサミ男が探偵役になる」という意外な構造が出来上がっています。
さらに、終盤で明かされる真相は、それまでの読者の認識を完全に覆します。
この作品では「語り手=犯人」という前提が巧みに利用され、読者は視点の操作によって真相を見抜けなくなっています。
このどんでん返しの仕掛けこそが、『ハサミ男』を唯一無二のミステリー作品へと昇華させているのです。
考察② 叙述トリックと倒叙ミステリーの融合
本作は、倒叙ミステリーと叙述トリックを組み合わせることで、独自の構造を生み出しています。
倒叙ミステリーとは、通常のミステリーとは異なり、犯人の視点で事件が進行する形式です。
これにより、犯人の心理や行動がリアルに描かれるため、物語の没入感が増します。
しかし、本作では単なる倒叙ミステリーに留まらず、語り手の視点に仕掛けられた叙述トリックが読者を翻弄します。
一見、語り手は「ハサミ男」であり、物語は彼の視点で展開されているように見えます。
しかし、細かく読み返すと、そこに微妙な違和感があることに気付くはずです。
この違和感が何なのかを明かした瞬間、読者はそれまでの物語の全てが異なる意味を持っていたことに気付きます。
倒叙ミステリーでありながら、途中で語りの構造を逆転させるという手法が、『ハサミ男』を独創的な作品にしているのです。
考察③ 作品に漂う不気味な雰囲気
『ハサミ男』は、独特な雰囲気を持つ作品でもあります。
殺人犯であるハサミ男が主人公であるため、通常の探偵小説とは異なり、常に不気味さが漂っています。
物語の舞台となるのは、無機質で冷たい都市空間です。
登場する喫茶店や街の描写はどこか寂しげで、読者に不安感を抱かせます。
また、ハサミ男が頻繁に訪れる喫茶店でのミートパイの描写など、日常的なシーンに違和感が織り交ぜられているのも特徴的です。
さらに、登場人物たちの台詞や思考にも不穏な要素が含まれています。
ハサミ男の語り口は独特でありながら、どこか冷静さを保っていますが、そこに潜む狂気が徐々に露呈していくのです。
読者は、彼の視点に引き込まれながらも、「この男を信用していいのか?」という疑念を抱くことになります。
このような不気味な雰囲気が、物語全体の緊張感を高め、ラストの衝撃をより一層際立たせる要素となっています。
まとめ
『ハサミ男』は、倒叙ミステリーでありながら、叙述トリックを巧みに仕掛けた作品です。
物語は二重のどんでん返しによって読者の予想を完全に覆し、その巧妙な構造に驚かされます。
また、語り手の視点に仕掛けられた叙述トリックが、倒叙ミステリーの枠を超えた斬新な読書体験を提供します。
さらに、物語全体に漂う不気味な雰囲気が、読者をじわじわと追い詰め、最後のどんでん返しへと導く役割を果たしています。
本格ミステリーの醍醐味を存分に味わえる『ハサミ男』は、ミステリー好きなら一度は読むべき作品です。
まだ読んでいない方は、ぜひ手に取ってみてください。